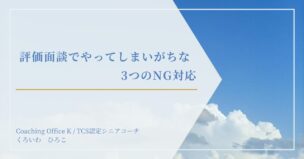
管理職やリーダーの方から多くご相談いただくことのひとつが「評価面談の進め方」です。
どんなに丁寧に話しても、相手が評価に納得しない。
○○さんより私の方が頑張っていました!という話ばかりで、具体的な成果の話にならない。
等々……
元々、管理職やリーダーになるような方は、目標管理への取り組み方や、成果の伝え方が上手な方が多いですから、こうした方との意識や捉え方のギャップに困惑する方も多いようです。
今回は、評価面談でやってしまいがちなNG対応について、3つ見ていきたいと思います。
「頑張っているのに、上司から評価されていない」と感じている部下の立場の方も、評価面談で同じポイントを意識することで、ご自身の成果が伝わりやすくなると思うので、参考にしてみてくださいね。
NGポイント1:ゴールを勝手に動かす
非常に多いのが、上司・部下のどちらかが、目標やゴール、すなわち「ここまで出来たら、今期はOK!」とする事項をいつのまにか別のものに変えてしまっているケースです。
実際に仕事をしていると、期初に目標設定やゴール設定をして、「今期はここまでできたら100点!」と決めていたとしても、期中に方針が変わった、あるいは、個人の置かれている状況が変わった……などで、その目標が消失したり、ゴールが変わったりするケースがあると思います。
その時に、「目標やゴールが変更になった」ということを明確に合意せず、そのままずるずると評価の時期まで保留にしてしまうと、本人からすると「そもそも不可能な目標」に対する「達成できなかったという事実」だけが残ります。
変わったゴールを上司が提示できていなければ、それは上司が勝手にゴールを動かしたことになります。
また、不可抗力であっても、部下の側は「達成できなかった」という事実を報告するのは結構ストレスが大きいです。
そのため、目標やゴールが変わったかどうかにかかわらず、達成できなかったことには触れずに、自分が達成できたことの中から評価されそうなものをピックアップして報告する……ということをすることがあります。これは部下がゴールを動かしているケースですね。
いずれにしても、合意した目標やゴールが明確でなくなった時点で、こうしたすれ違いが起こりがちになります。
すれ違いを防止するためにも、評価の話をするときは、「そもそも今期の目標やゴールは何だったか?」からスタートする形で進めるのがいいかもしれません。
NGポイント2:本来の評価軸と異なる評価軸で話す
2つ目が「本来の評価軸と異なる評価軸で話す」です。
もしかしたらジョブ型を導入した企業で多く起こっているのではないかな?と思います。
日本でかつて一般的だった「職能資格制度」。
これは「社員を職務遂行能力によって等級分けし、職務遂行能力のより高い人により高い給与を払う」仕組みでした。
職能資格制度における評価は、「その等級で想定されている能力が100%発揮出来たら満点」というケースが多かったのではと思います。
等級という形で査定されている、期初時点の能力以上の力を発揮できたら加点対象です。
ジョブ型はこの点、考え方が異なります。
ジョブ型は「ジョブ=業務の内容と責任の重さ」を(会社によっては)レベル分けし、ジョブに応じて給与を決める仕組みです。
なので、ジョブ型での100点満点は「割り当てられた業務と責任を過不足なく果たせた状態」です。
本人の能力は関係ありません。
本来割り当てられた業務や責任を超えて出した成果があれば、それが加点対象となります。
すでにジョブ型の人事制度に移行しているにも関わらず、本人あるいは上司が「本人が100%能力を発揮できたら満点」という、職能型の発想で評価について話をしてしまうケースがかなりあるのではと感じます。
が、会社としての評価は、ジョブ型導入企業であれば、当然ジョブに沿って判断されます。
結果として、本人が「思ったように評価されない」という、納得度の低い状況になってしまうわけなんですね。
NGポイント3:成果と成長を区別せず話す
さて、3つ目のNGポイントは「成果と成長を区別せず話す」ということです。
これも、特にジョブ型の人事制度を導入している企業で重要になってくるポイントです。
前項でも触れた通り、ジョブ型の評価においては、本人の能力は関係なく、「割り当てられた仕事をできたかどうか」が評価基準となります。
つまり、「本人が成長したかどうか」は、基本的には評価されないということです。
※会社制度により、程度に差があると思いますので、ご自身のお勤め先の制度を確認してくださいね。
同じ仕事をしている限り、昇格などもないですから、特にルーティンワークが中心の人は、仕事の中での成長を感じにくくなります。
こうした状況は、人によってはモチベーションや、会社へのコミットメントを大きく損ねます。
「こんなに成長したのに、会社は評価してくれない!」というフラストレーションが溜まるからです。
そのため、評価面談にあたっては、成果とは別に、本人に「どこがどう成長したか」を明確に伝えていくことが必要となってきます。
給与等に反映されないとしても、自分のがんばりや成長に気づいてもらえているか、は、人の意識に大きく影響するものです。
また、成長について、分けてフィードバックすることで、上位の職務へのチャレンジを提案するきっかけにもなります。
おわりに:評価面談は目標設定のときから始まっている
さて、ここまでお読みになった方で、こうお感じになった方、いらっしゃるのではないでしょうか。
「そもそも、期初にどんな目標を設定したかによって、評価面談の質が変わってくるのでは?」
はい、その通りだと思います。
評価面談は、評価のタイミングでだけ気を配っても、良いものにはなりにくいです。
どのような目標を設定したか?
期中、その目標に対して上司・部下がそれぞれの立場で、どのようにかかわってきたか?
により、評価面談の質は大きく変わります。
なのでぜひ、どのような目標を設定すれば、そして、期中どのように相手と関われば、より評価しやすいか? 評価の納得度が上がるか? についても考えてみていただければと思います。
ジョブ型に移行することで、評価面談は、よりキャリア支援の側面が強くなってきているなと感じます。
コーチングを学んだ方は、力の発揮のしどころですよ。
コーチングを学んだことがない方は、ぜひこれから、目標設定や評価の精度を上げるためにも、コーチングの活用も検討してみていただければと思います。




